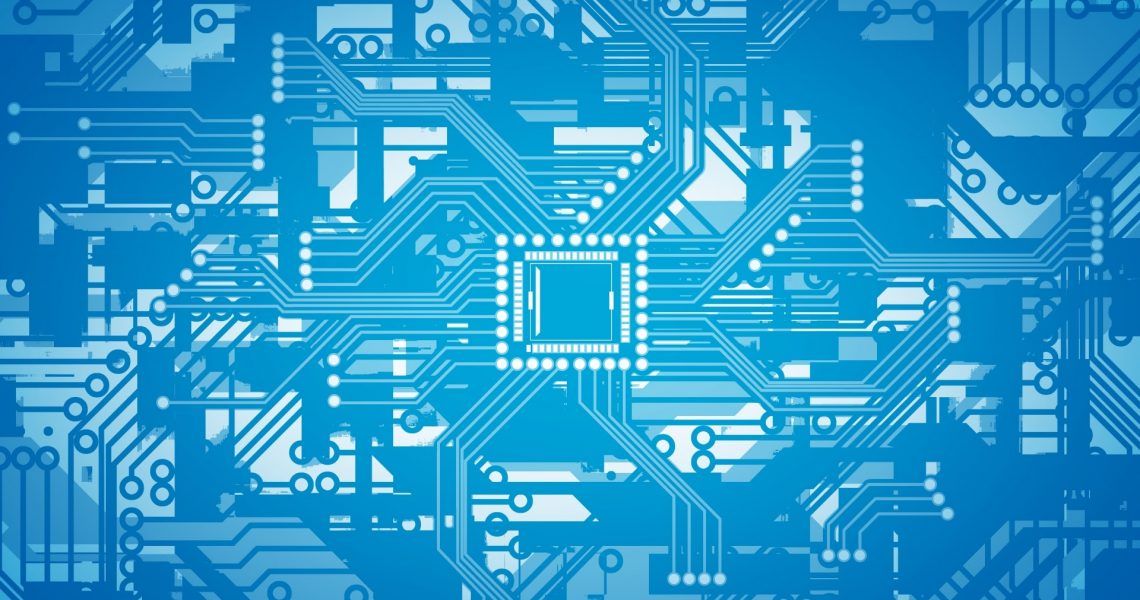AIの歴史 – 第一次AIブーム –
先日最先端を走るアメリカ企業のテスラ社が人間型ロボット「Tesla Bot」を発表しました。AIを搭載したロボットが危険な肉体労働を人間の代わりに行うことを目的としているようです。「遂にSFが目の前に迫ってきたな」と思わされます。
SFというジャンルに拘らず、人間の代わりに働くロボットのような存在が古代の神話から「ゴーレム」などの形でありました。古代からずっと人間は「人間の代わりに働いてくれる存在」を欲しがっていたわけです。
人型で機械仕掛けという想像上の存在が一般的なものとして普及したのは、日本ならやはり「鉄腕アトム」のおかげでしょう。鉄腕アトムが世の中に登場したのは1952年。
ちょうどこの後に第一次AIブームが起きたと言われています。
今日はこのAIブームの内容を中心に、「人間の代わりに働いてくれる存在」を実際に作ろうとしているAIの歴史と進化のスタート地点を知っていきましょう。
AIの誕生
最先端のイメージがありますが、AI(Artificial Intelligence )という言葉が生まれたのは1956年にアメリカで行われたダートマス会議です。
この会議の中で紹介された「Logic Theorist (ロジック・セオリスト)」が世界初のAIプログラムでもあります。
このAIプログラムで出来ることはプリンキピア・マテマティカという本に掲載されている数学的定理の証明です。冒頭に記載されている52の定理の内、なんと38の定理の証明に成功しました。
プログラムが定理を証明するということ自体が革新的ではありますが、この「Logic Theorist」で使われている要素の内には現代でも使われているアプローチがあります。
それが探索木とヒューリスティクスです。
上記が代表的な探索木である「二分探索木」です。
探索木ではそれぞれのノードで設定された規則で計算を行います。異常のない結果が得られた場合、更にその結果から次の計算を行います。異常のある場合は親ノードに戻って異常のない結果がでるまで再計算し、計算を繰り返して掘り深めて設定しているゴール(仮説通りの値)の値を取得します。
分かりやすい例は以下です。
しかし問題によっては、計算結果が設定上異常のない値でも、探索枝が指数関数的に増大し、ずっとゴールに辿り着けないことがあります。そういった場合、人間が計算をしてるなら早々に異常に気づいてその枝の計算をはしないという判断ができます。しかし、定式化した計算を繰り返してゴールを探すプログラムでは気付けません。ずっと計算を続けてしまいます。
そういった、人間的に見て間違っていそうなパターンを排除するのがヒューリスティック(発見法)です。もちろん、一見間違ってそうに見えて解に向かっている場合もあります。この場合、ヒューリスティックのせいで解が得られなくなるということもあります。
ざっくり言うと、法則に従って総当たりでゴールを得るのがアルゴリズムであり、客観性があります。
一方、振る舞いを見てゴールを得るのがヒューリスティックであり、人間の感覚的な正しさはありますが、論理だった客観性はありません。
ヒューリスティックの例① 暗証番号

アルゴリズム
0000番から9999番まで総当たりで入力していく
➡︎時間がかかる
ヒューリスティック
持ち主の誕生日や電話番号などの情報を入力する
➡︎絶対にわかるわけではない
ヒューリスティックの例② コンピューターウイルスの発見

アルゴリズム
特徴的なパターンのコードを探す
➡︎合わないと見つけられない
ヒューリスティック
特徴的な挙動を探す
➡︎誤判断してしまう
第一次AIブーム(1960年代)
この会議の後、計算する機械にすぎなかったコンピューターが探索や推論ができるものと認識され一気に人工知能の研究が活発になってきました。
パーセプトロン
この時期に作られ、多くの面で概念が「パーセプトロン」です。
これは機械学習の祖ともいうべき概念であり、今でも機械学習を学ぶ際に必須の存在です。
上記がANDゲートのパーセプトロンの例です。バイアス(負の数)を、入力と重みの積の合計が上回っていれば1、そうでなければ0を返すものです。他にも出力の部分(活性化関数)を変えることで出力の形を操作できます。他にもOR・NANDがあります。
視神経と脳細胞のニューロンモデルが抽象化されたモデルとなっています。
上の図を見て「なるほど…」と言える方はかなり数学的なセンスがある人だと思います。
大多数の人は「えっと、何?」となると思います。
分かりやすくするため、下の猫のイラストで考えてみます。
一番上の猫の耳のパーセプトロンの式を以下とします。
入力合計=バイアス + (入力①✖️重み①) + (入力②✖️重み②)
入力合計 > バイアスなら 出力=1
入力合計 ≦ バイアスなら 出力=0
まず一番上の耳の部分のバイアスと重みです
バイアス= -1
耳の「尖り具合」の重み:1.5…重み①
耳の「間隔」 の重み:0.5…重み②
入力が
耳の「尖り具合」:猫かな?0.6…入力①
耳の「間隔」 :猫かな?0.5…入力②
入力を式に代入すると、入力合計は1.15となり、バイアスの -1 を超えます。
よってこれは猫の耳と判断され、1を出力します。
同様に「目・鼻・口」の形状や「アゴ」の形状を判定するパーセプトロンが「猫のものである」として1を出力します。
そして更に猫かどうかを「耳」「目・鼻・口」「アゴ」の入力で判断するパーセプトロンがあり、各1の入力があり、重みとの積がバイアスの値を上回るので晴れて「これは猫のイラストだ」という判断がされます。
以上が「猫のイラストかどうか」の簡単なパーセプトロンが使われるケースのイメージです。
なお、実際にパーセプトロンが使われる時は逆のパターンです。
「猫」と「犬」のイラストをたくさん機械に見せることで、最初はランダムで入力されるバイアスや重みを少しずつ修正して、猫らしいものが判断できる重みとバイアスを得るのが機械学習です。
ELIZA
他にもこの時代で特徴的な成果があります。1966年にELIZAです。
ELIZAはテキストで対話できる自然言語処理プログラムです。つまり、テキストチャットができるAIです。現代のSiriの祖先に当たります。
入力される会話文に対して人間的な回答をしてくれるものです。
どんな仕組みなのかというと、入力された内容を今で言うデータベース内で検索して、設定された内容を返すというものです。現代では当たり前の方法ではありますが、パソコンすら登場してないこの時代では画期的なもので、当時の人々に大きな衝撃を与えたようです。
wikipedia: ELIZA(https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA) より
ブームの終焉
1960年代の終わりとともに、第一次AIブームは終了します。
現実世界にはAIはまだまだ対応できそうにない、という現実が明らかになったためです。
一番最初のアルゴリズムとヒューリスティックの組み合わせでも全ての定理が証明できるわけではありませんでした。
次のパーセプトロンにしても、この段階では単純パーセプトロンと言われる「入力」「出力」の2層しかないもので、線形分離可能なものしか区別できないという問題を抱えていました。かなり噛み砕いて言うと、青とそれ以外の色を分けようとした時に、水色や群青色のような存在を切り分けられないというものです。使える部分が大きく限られてしまいます。
ELIZAもコンピューターが言葉を理解しているわけではないため、パターンマッチの外にある内容については対応できません。
そして更に当時のAIそのものに対する大きな期待に対して応えられないことがはっきりした問題も提議されました。「フレーム問題」という問題です。
人がコンビニにカップラーメンを買いにいくとします。人間であれば「安全に行って帰ること」はなんてことはありませんが、AIの場合、まず「安全に」がとても難しいことです。
通常考えなくていい「飛行機が落ち来ないか」「隕石が落ちてこないか」ということも判断したり、逆に「考えなくていい」という判断をしなければなりません。つまりありとあらゆることに対して、判断するにしても判断しないにしても「考える」という処理をする必要が必要になり、膨大な時間が必要になります。
AIが人間の代わりに働くということが現実的ではないと分かってしまったのです。
まとめ
第一次というだけあって、その後の技術のベースになるものが多く登場し、また現代にも続く多くの問題も発見されました。コンピュータそのものの能力も低く、パソコンというものすら登場していない時代にここまで進んだのだと思うと、尊敬の念と現代社会の素晴らしさを感じますね。
現代のAIも解決できない大きな壁もチラホラみえてきています。
何ができて何ができないのかを判断するには自分が確かな知識を知っていなければわかりません。歴史から学べることも多いです。来るAI社会のためにも、少しずつ知識を増やしていきましょう。
中小企業をがっつりサポート!
当社では
など、企業のIT化のサポート・DX事業のサポートを行っています。
まずはお気軽にお問い合わせしてください。